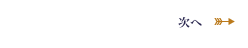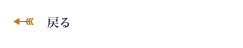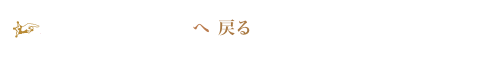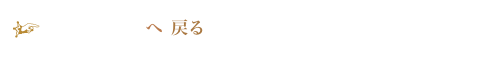My Singapore Life 2009


My Singapore Life 2009

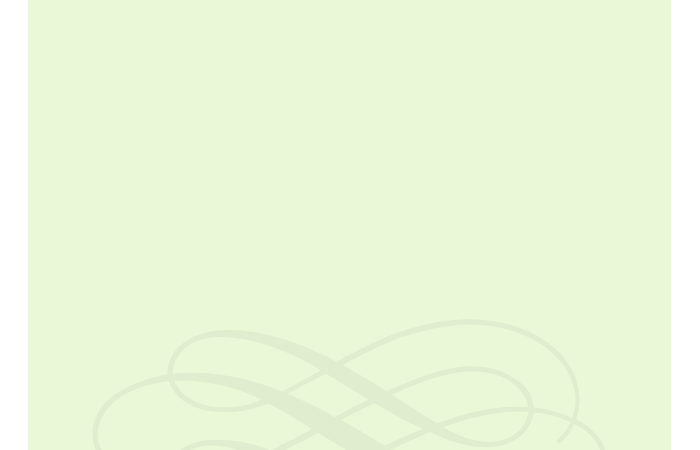
シンガポールの歴史的・文化的背景を語る上で欠かせないのが ペラナカン(プラナカン)。
ペラナカン料理、もしくはニョニャ料理という言葉を聞いた方もいらっしゃるかもしれません
ペラナカンの語源はマレー語のanak(~の子供、~の生まれのという意味)の言葉からきており、東南アジアのマレー語文化圏において、「混血の人々」を指しています。
ペラナカン(プラナカン)とは、14~15世紀頃に始まった「マレー半島にやってきた移民の子孫とその文化」を指していますが、ペラナカンという言葉を使う様になったのは実は最近、世界大戦後の事で、この地に入ってくる労働者と区別する為にそう呼ばれる様になったそうです。
ペラナカン博物館は、20世紀初めに立てられた旧タオ・ナン・スクールの建物を使用した小さいながらとても美しい博物館です。
ペラナカンの婚礼を軸に、様々な銀製品や磁器、宝飾・服飾品などを展示し、その文化や生活様式を貴重なコレクションや再現ビデオなどで紹介しています。
マレー、中国、オランダ、イギリス、ポルトガルなどの文化が融合した独特の文化を紹介したペラナカン博物館は一見の価値あり。
美しい色とりどりの装飾品や婚礼の品々など、貴重なコレクションを是非お楽しみください。
当サイトではペラナカン博物館 に展示されている貴重なコレクションをほんの少〜しだけ紹介しています。(写真はスライドショーにて、大きな画像も見る事ができます。)
Peranakan Museum Tour

東南アジアは海上交易の十字路に位置し、古くは平安時代後期より沢山の商人達が貿易風を利用して、中国大陸やインドなどからマレー半島に渡来しました。
中国大陸からの貿易船は11月頃からの貿易風に乗ってやって来て、風向きの変わる5月頃に帰って行き、また5月からは反対にインド方面からやってくる貿易船で大変賑わってそうです。こうして東南アジアは一年をとおして遠く異国の地からさまざまな民族・文化が入ってきていた場所だったのです。
***
そしてこの商人達の中に、現地の女性と結婚しこの地に根を下ろした人々がいました。
その子孫が今日のプラナカンの始まりです。
ペラナカンの人々は海上交易で財を成した比較的裕福な商人が多かった事、そして災いを避け縁起の良い物を好み、富を顕示する事を好んだ彼らの気質も、彼ら独自の文化が発展していった要因でしょう。
ペラナカン博物館では、東南アジアでも最も大きなコミュティである中国系ペラナカンに焦点を当てて紹介していますが、ペラナカンにはインド系ムスリム(Jawi Peranakan)やムスリム以外(キリスト教やヒンズー教)のインド系(Chitty Melaka)のコミュニティもあります。
博物館1階のギャラリー1では、こうしたシンガポールのペラナカンの人々を紹介する共に、ペラナカンの始まりについて紹介しています。
シンガポールのあちこちで目にする「ニョニャ料理」のニョニャですが、Nyonya (Nonya) :ニョニャ or ノニャとは、ぺラナカンの女性のこと。
ペラナカンの女性は大変料理が上手だったらしく、ペラナカンの料理を今日ではニョニャ料理とも呼んでいるのです。
ちなみに、ペラナカンの男性の事はBaba:ババといいます。
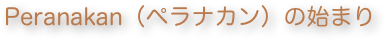
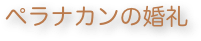
博物館2階のギャラリー2〜5では、ペラナカンの婚礼についての展示を軸にペラナカンの人々の暮らしを紹介しています。こちらは本当に見所満載ですよ。
ペラナカンの人々は裕福な商人が多かった上に、自らその豊かさを誇示するのを好んでいたので、婚礼などはその絶好な機会だった為、婚礼の品の数々は目を見張る程の豪華さです。

中国からもたらされた美しい吉祥文様は、ペラナカンの人達が特に好んだ装飾です。
繁栄を意味する鳳凰、花の豪華さから富貴を表わす牡丹、相思相愛や長寿 を表す蝶(中国語で蝶を「ディエ」と発音し、「耋(ディエ)」の発音が同じことで長寿の意)、葡萄や柘榴(ざくろ)は子孫繁栄、そして草花や龍(長寿・権力)や鹿(おめでたい言葉と同じ発音だった)などの動物などの図柄も好まれました。
花嫁は長い髪を龍の様に巻き上げ174本のピンで留めてこの豪華な冠をかぶったそうです。
ネックレスの上の星形のブローチは、本物の93個のブリリアンカットのダイアモンドを使用した大変豪華な物です。
これらの豪華な装飾品は、景気が悪くなるとお金に換える事も出来た為、婚礼の品にお金をかけどんどん豪華になっていきました。
もちろん全てのペラナカンが裕福だったわけではありませんので、レンタルもあったそうです。
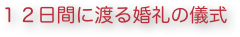
ペラナカンの女性は12歳くらいになると、滅多に外に出ることが出来なくなりビーズ細工や刺繍等の花嫁修業を始めたそうです。
ペラナカンのお家の2階のお部屋の床には小さな覗き窓が付いていて、ジュータンをぺろんとはがして覗き窓を開け、1階の様子を覗き見る事が出来たそうです。
女性は隔離された状態で暮らしていたので、こうしてこの覗き窓から訪れた客人の様子をこっそりと覗いていたのだそうです。

なんだか胸が締め付けられる思いがしますね。彼女達が将来自分の夫となる男性に贈る為に、丹誠込めてこつこつと作った可愛らしい贈り物の数々も展示されています。
それらを見ていると、当時の女性達の事を想い本当に切なくなります。
ペラナカンにおいての成人は現代に比べて大変早く、結婚適齢期は男性は16から18歳、女性は14歳~16歳だったそうです。

結婚相手は親や親族によって互いの家柄、経済状況を吟味した上でまず候補者が選ばれました。
そして結婚の日取りや相手は最終的に八字(ぺクチー)という占いで決められ、婚礼の当日までお互いの顔を知らないままの結婚でした。
婚礼の儀式は花嫁の実家で12日間に渡って行われ、花婿はその間花嫁の家に通い続けるのです。
ギャラリーでは、ペラナカンの12日間に渡る婚礼の儀式の様子を様々な展示物で紹介しています。
花婿から花嫁へ、そして花嫁から花婿へ贈る婚礼の品(結納品)も展示されています。
中国の影響でしょうか、げんを担ぐ様な品々が多く、おめでたい色とされる赤い色を用いたもの(家を守る神様にお供えする赤いロウソクなど)が多かったり非常に興味深いです。
花婿から花嫁へ送られた品は(おめでたい時の定番!の)みかん(12個:1年は12ヶ月だから)や、豚肉、婚礼衣装用の布、宝飾品や銀製品など。
花嫁は花婿をたてるために半返しよりも少し多めに結納返しをしました。
ベルトや指輪、時計などの宝飾品、みかんは8個(半分よりも多めに。代わりにロンガンを足して)、豚肉(もらった量よりも少なめ)、甘い生活を・・・ということでシロップ、送られた生地で作った服や、花嫁お手製のビーズで作ったスリッパなど。。。
ペラナカンの女性にとって、ここは腕の見せ所。
彼女達はビーズ刺繍の腕前で女っぷりをはかったそうです。
まだ互いの顔も知らない花婿と花嫁・・・・。
婚礼の第一日目に行われる「髪梳きの儀式」で始めて二人が出会うわけですが、この儀式ではまだお互いの顔を見る事ができません。
豪華な家具で飾られた花嫁の家(実家)を模したギャラリーでは「髪梳きの儀式」の様子を再現しています。
婚礼の第1日目に花婿は花嫁の家を訪れ、家の守り神を祀った祭壇や親族の前で最初に行う「髪梳きの儀式」という成人になる為の儀式を行います。先祖にこの結婚を認めてもらう為の儀式でもあったので、ご先祖様の写真なども置いて執り行いました。

鏡をあてるのは物事の真贋を見極める力がつく様に、
櫛を髪にとおすのは何事もスムーズに事が進む様に、
カミソリをあてるのは物事に慎重になる様に、
天秤をあてるのは物事を正しく推し量れます様に、
ハサミをあてるのは互いに助け合って協調性を重んじる様(ハサミの刃は一つでは切れない)に、
そして床に置かれた赤い花(Ixora:イクソラ=サンタンカ)とネギは魔除けを意味します。
ちなみに、Ixora(イクソラ)はサンスクリット語の「シバ神」をポルトガル語訳した言葉です。
シバ神にこの花をお供えしたことに由来します。
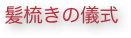

ペラナカンの豪華な婚礼家具の中でひと際目を引くのが 、Ranjang Kahwain(婚礼用ベッド)です。Ranjang Kahwain(婚礼用のベッド)は、花嫁の実家の最も日当りの良い部屋に置かれました。
花婿は婚礼が行われる12日間、毎日花嫁の実家に通い、朝まで花嫁と一緒にこの部屋で過ごすのです。
婚礼用のベッドは豪華な装飾や吉祥文様の飾りが施され、寝具も色とりどりの刺繍で大変美しく飾られました。ペラナカンでは、良い香りは邪気を祓うと信じられていおり、香水を用いたりお香を焚いたり香りの良いお花を部屋に置いたりしたそうです。

花嫁の部屋を再現したギャラリーには、タッチパネルが設置してあり花婿と花嫁の感動のご対面の様子が再現映像で紹介されています。
待ちに待った対面を果たした花嫁と花婿は、まずこの部屋で一緒に食事をし、食事をしながらお互いの足を踏み合う遊びをしたりしたそうです。
女性の方が先に足を踏んだら、その家庭はかかあ天下になると言われていたそうですよ。。。
婚礼が行われる前に、実はこの婚礼のベッドで必ず行う需要な儀式がありました。
まず占いで親族から男の子が選ばれます。
そしてその選ばれた男の子が赤い服を着てベッドの上をごろごろと転げまわり元気な子供が産まれる様、男の子が生まれる様「気」を授けるのです。
この婚礼の12日間の間、ベッドの下にはタロイモや紅白のお餅のシロップ漬けがお供え物が置かれたそうです。この暑さにくわえ12日間も放置されたこのお供え物・・・・当然、このお供え物には虫がわいてしまうのですが、虫が沢山わけばわく程子沢山になる・・・と信じられていたそうです。

婚礼の儀式の三日目に、花婿が親族やご先祖様に跪(ひざまず)いてお茶を差し上げる儀式を行いました。
ギャラリーでは花嫁お手製の可愛らしい膝あてが展示してありますが、この儀式の時に使用するのです。

この婚礼行列では、まず先頭に両家の名前の入った提灯を持つ人、花嫁、花婿、Wedding boy,Wedding girl、花嫁行列に参列する人達はご主人が健在で子供のいる女性が選ばれました。(縁起が良い為)
婚礼のお祝いの品は、豪華なお盆に載せて恭しく運れたそうです。
花婿の家でも同じ様にまず「髪梳きの儀式」など、同様の儀式が行われました。
花婿の玄関口には名前や職業、おめでたい文字が入った提灯がさがっていたり、狛犬がいたり。
玄関のドアは風通しが良い様に上半分が開いていたり格子状になっていたり吉祥文様が施されていたりしてとても豪華な造りでした。
花婿の実家の玄関を再現した展示では、当時の雰囲気を感じる事ができます。
ペラナカンの女性の嗜み(たしなみ)とされたのが、シレーチューイング(Sireh-chewing)という習慣でした。
このシレーチューイング(べテルナッツチューイングとも言います)は、中国沿岸部から南はインドネシア、東南アジア全域、そしてアフリカの西海岸広まっていた慣習なのだそうです。
ペラナカンでは男性が煙草を吸うのに対し、女性はこのシレーを愛用しました。
今現在では、歯が黒く変色したり、発がん性が指摘され口腔ガンの原因になる・・・などの理由により一部地域のお年寄りの間でしか見られなくなってしまいましたが、今でもリトルインディアなどで普通に購入する事ができます。
シレーの葉(胡椒の仲間キンマの葉)の上に石灰ペーストを塗ってヤシの一種のアリカナッツ(檳榔樹(ビンロウジュ)の実=檳榔子(ビンロウジ))を薄くスライスしたものに、ギャンビアやドライココナッツ、サフラン、砂糖、クローブ、カルダモン、ターメリックなどのスパイスをお好みで混ぜ、刻みタバコ、蜂蜜などを加えて、一口大の大きさに巻きます。
それを口の中でくちゃくちゃと噛むと口の中がスッとするそうです。
シレーチューイングをすると口の中が赤くなるそうですが、赤くなった唾は飲み込まず(葉っぱも最後まで食べず)に、ベドゥと呼ばれる痰壷に吐き出します。
檳榔樹の実にはアルカロイド(窒素化合物)が含まれており、この成分の働きにより一種の麻薬作用を示し、常習性があるそうです。
シレーの葉、そして中に入れるスパイスを収めたシレーボックスには、金銀や貝殻などを使い非常に細かい細工が施され、プラナカンの豊かさの象徴でもありました。
またシレーボックスには、魔を払う絶大な効果があるとされとても大切にされたそうです。
もちろん婚礼の間、花嫁の部屋にも置いてありました。
プラナカンの社会においてシレーチューイングは単なる嗜みである以上に、生活の中で歓迎の印と考えられていました。お客様を家にお迎えすると、まずシレーチューイングをお薦めするのが良いおもてなしとされ、ゲストもこれに応じることで歓迎を受け入れたことを示しました。
また、シレーチューイングをしない人は、シレーボックスに触れることで歓迎を受け入れたことを表したのだそうです。。。
また婚礼の儀式においてシレーボックスは特に重要な意味合いを持っていて、最終日に花嫁の貞節が疑わしいと思った花婿はシレーボックスをひっくり返すことによって、結婚を取りやめるサインにしたそうです。
こういった風習から、ペラナカンの人達の間では様々なシチュエーションでこのシレーボックスを使って気持ちを表現しました。
シレーボックスに触れたらOKサイン、シレーボックスをひっくり返すとNGサイン・・・といった具合に。
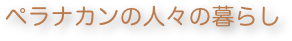
お葬式では、足を外向けにして棺が置かれ、ご遺体には奇数の枚数の服を着せられました。
地位が高ければ高い程、大きな数の奇数(7枚とか9枚とか)の服を着せられたそうです。
そしてご遺体の口の中にシレーの葉っぱで包んだ真珠を入れたり、おなじく足元に真珠を入れたそうです。
これは亡くなった人が突然蘇ってしゃべり出さないように、滑って立ち上がれない様にというおまじないだそうです。
ロウソクや祭壇やお供えのお花、香典袋も白。
お供え物の食器も白地にブルーと地味なものを使用します。
お葬式に参列した人は、帰りに2本の赤いロウソクと一本の赤い糸をもらって帰ります。
帰り道に赤い糸を道ばたに捨て、家に入る前にロウソクを燃やしてお清めをしました。
(これは中華系のお葬式と一緒ですね)
遺族(特に未亡人?)は3年間、喪に服します。
最初の1年目は黒い服を、2年目はグレーの服、3年目は地味な色の服を着て過ごします。
3年間の喪が開けると、玄関に赤い布をかけ喪が明けた事を知らせるそうです。

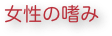

博物館3階のギャラリー6〜9では、ペラナカンの宗教やお葬式、喪に関する展示の他、大変貴重なニョニャウェアのコレクションの展示と共に人々の暮らしについて紹介しています。
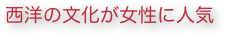
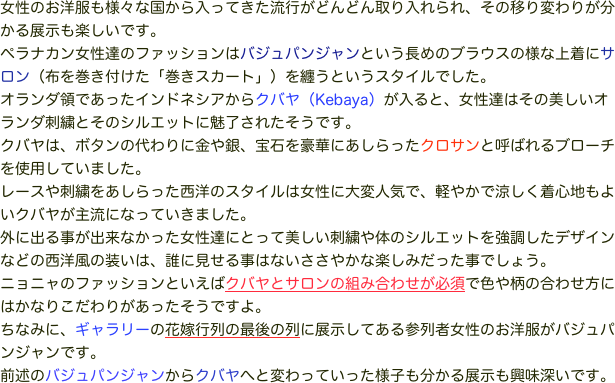
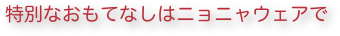
ペラナカンでは、お客様がいらした時は、特別な食器でおもてなしをします。
それらの縁起の良い吉祥文様やカラフルな配色の磁器は、今日ではニョニャウェアと呼ばれています。シンガポールに来た事がある方なら、一度は目にされた事があるかもしれません。
とりわけ、名前入りの特注の食器は大変豪華な物で、これらの食器を使ったお食事は最高のおもてなしとされました。
展示物の中には高価な景徳鎮のKamcheng(蓋付きの食器)や有田で焼かれた物もあります。
博物館3階のギャラリーでは、当時のキッチンを再現した展示もあります。
水を保存する為のかめ、虫除けの為のキッチンネット、そして冷蔵庫のなかった時代ですから、風通しの良い高い所に食べ物を吊るす為の籠(鳥籠の様な形)などを見る事ができます。
キッチンを守っていたかまどの神様が旧暦の12月23日に天界に上りこの一年その家にあった事を天界の神様に報告し、お正月の3日に戻って来るそうです。
都合の悪い事を報告されたくなかった女性達は、よく水飴をお供えしたそうです。(水飴はねばねばしているので、食べると口がネバネバしてしゃべれなくなると考えられていた)
「▶スライドショーを再生」をクリックすると、大きくて綺麗な画像を見る事ができます。
是非お試しくださいね!
20世紀初めに立てられた旧タオ・ナン・スクールの建物を使用し、ペラナカンの婚礼を軸に、様々な銀製品や磁器、宝飾・服飾品などを展示し、その文化や性格様式を貴重なコレクションや再現ビデオなどで紹介しています。
MRTのシティホール駅から徒歩10分で、入場料は大人5シンガポールドル、子供2.5シンガポールドル。
▽プラナカン博物館開館時間
月曜日:13時00分~19時00分
火~日曜日:09時00分~19時00分
金曜日:09時00分~21時00分